|
近代符号速記法は、受動的な環境で、あらゆる発言をありのままに固定するた めに、筆記の高速性と逐語性を備える符号派へと発展してきた。その符号研究と 国字との関係ではその言語における文字言語の影響を強く受けてきた。符号以外 にも、書字方向はその言語の文字習慣に基づいて行われる傾向があり、英語速記 法の場合、左起右進横書きが主流であり、縦書き文化へ移転する際にもその書記 方向が強い影響を与えた。
日本語の表音主義の速記法では、このような欧米語の速記の工夫を参照しなが ら日本語の特性に応じた縮記法、略記法、省記法によって、発言された言葉を示 す速記符号を表記できる体系を整えている。この報告でで論じる日本語速記法に おける基礎符号の数は、一応五十音図で読みが使われている44音としている。 一方、符号派においては、発言事実に忠実に発言記録を作成するために、速記 法体系は個別略語体系主体の比重を減少しながら、ミニマルペアのような音韻上 の規則性、文法規則、言葉の発想メカニズムなど、その言語の法則性に基づいた 省略、縮記体系が開発されてきた。 また、ピットマン式が絶対的な理想体系と位置づけられていたものの、日本語 文字の筆記慣行から実際に筆記される速記符号は理想形態から離れていくことに なった。ピットマン式が速記書で示した速記符号は知識として与えられるイメー ジであり、心象として記憶される。それは直線、曲線いずれも付属情報が付加さ れたあるべき姿であって、筆記によってあらわれる速記符号は手指、書き手の精 神状態によって理想の心象とかなり違ってきてもおかしくない。しかし、この符 号の崩れは解読できなくなるリスクを伴う。そこで、知識として示す符号の外見 を崩れ要素を織り込んだ現実的な符号とする動きが次第に主流になってきている。 田鎖式の派生方式である衆議院式標準速記法では、このようなあるべき姿を静態 符号、一方現実に筆記される形を動態符号として、両者の関係を肯定的に認めて、 反訳リスクを解決している。反面、中根式から派生した正円・楕円幾何派の国字 式、山根式では動態符号を認めないため、認識上のリスクが顕在化するなど、課 題も生んだ。
|
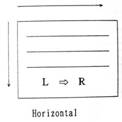
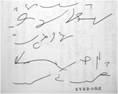 英語では速記アルファベットは最初、文字に対応して設計され、次に発音どお
りに固定するために音素符号が開発された流れに並行して、高速度を追究して符
号の筆画数を減少させる単画化への方向性を示した。速記符号は、罫線ノートの
罫線上にストロークを置いて加点母音や母音サインを連綴する形式で行われたが、
次にはそれをゾーンの帯域上でストロークの長さを変化させる等によって音素、
音節を表記する方向へ発展していった。
英語では速記アルファベットは最初、文字に対応して設計され、次に発音どお
りに固定するために音素符号が開発された流れに並行して、高速度を追究して符
号の筆画数を減少させる単画化への方向性を示した。速記符号は、罫線ノートの
罫線上にストロークを置いて加点母音や母音サインを連綴する形式で行われたが、
次にはそれをゾーンの帯域上でストロークの長さを変化させる等によって音素、
音節を表記する方向へ発展していった。